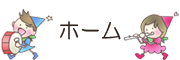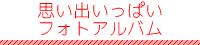上天草の慈愛保育園 ,熊本県上天草市大矢野町中の慈愛保育園は、子供たちの自主性を育てる保育園です。
楽しく♬おいしい♡給食の時間
離乳食に慣れてきました。自分で食材を指でつんつんと確認します。そしてこのあとパクっ!!ボイル野菜もしっかりと噛んで食べました。
口に入れて「ちょっとちがうな」と思ったものは舌を使って上手に口から出します。どんなに小さな子どもでも自分の食べ物の好みはあります。それが日によって違っていたりもします。体調や気分でも食の好みは変わってくるのです。
だから子どもたちには決して無理に食べさせるようなことはしません。無理に口の中に入れたりすると窒息の原因になってしまいます。
病気上がりだから食欲が落ちているな~、今日はお腹いっぱいみたいね、などと子どもの様子をよく感じて子どもたちが自ら食べたいと思い気持ちを高める支援をしています。
1歳児のお友だちです。スプーンでお口まで運べるようになりました。
2歳児のお友だちです。完食寸前に行ったので、ほぼ食事は終わっているところでした。何でもよく食べてくれるようになりました。
3歳児さんです。お箸をとてもきれいに使えます。お皿も抱えて口まで持っていきます。
緑の豆だって食べてくれます。緑色のお野菜は苦手な子どもも多いのですが、結構食べてくれますよ。
4歳児さんです。今日のみそ汁にはたまねぎ、にんじん、とうふ、麩、ねぎが入っていました。
出汁はいりこ、昆布、かつおぶしでとってあります。慈愛保育園の給食の先生たち、とっても頑張っているんです。
子どもたちの身体のために毎日出汁をとってくれます。おかげでとてもおいしいお汁を毎日いただいています。

給食もおやつも毎日ほぼ手作りです。子どもたちの身体のために作ってくれています。
給食もおやつも毎日ほぼ手作りです。子どもたちの身体のために作ってくれています。
私が子どもの頃は苦手なものも食べなくてはいけなくて、食べるまで残されて昼休み遊べず、泣きながら、結局丸のみして胃袋に入れていました。もしかしたら、のどに詰めていたかもしれないですね。のどに詰めなくてよかったです。
そんなわけで偏食の私は毎日の給食が、家族で食べる食事がとても苦痛でした。いまでもその食材だけはどうしても食べることが出来ません。無理して食べてもおいしくないし、身体にも心にも良くないです。
今は時代も変わり、小学校でも居残りで給食を食べることはないようです。それよりも「食べれません」「残してもいいですか?」と聞けるようになることが大事です。また食べる事への意欲を育むことが大事です。
もちろん、全く食べませんをそのままにほおっておくことはしません。色々な面から子どもたちの「食べたい気持ち(食欲)」にアクセスします。そしてすこしづつ食べられるようになるのです。
先日うまれてから、40年、「醤油の実」が食べられなかった職員が食べられるようになりました。ちょっとだけ味見をしたら「うまーい!!」と。
30年間食べられなかったピーマンやゴーヤが大人になったら嗜好が変わって食べられるようになりましたという彼・・・
私のように今でも食べられないものがある人もいますが、大人になるにつれて食べられるようになるんです。
だから・・・子どもの頃の今は食べることを楽しいと、おいしいと、思える食事がしたいものです。そして、少量でもいいので体にいいものを口から身体の中に入れる・・・それが大事ですね。