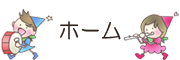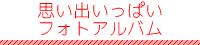上天草の慈愛保育園 ,熊本県上天草市大矢野町中の慈愛保育園は、子供たちの自主性を育てる保育園です。
今日は避難訓練をしました。
今日は地震から津波発生の大規模災害を想定しての避難訓練をしました。お昼寝の時間に地震が発生したら・・・を想定しての訓練です。
まず、室内に集まって地震、津波発生の訓練をすることを子供たちに伝えました。そして、避難の方法を教えました。
そして、各保育室に戻り、お昼寝をしている状態にします。毛布をきて横になります。
地震発生のベルが鳴ります。
テーブルが近くにある園児は毛布とともに机の下に入ってくれました。
揺れがおさまったので頭を守りながら第一避難場所の運動場へ逃げます。「お・か・し・も」・・・「おさない」、「かけない」、「しゃべらない」、「もどらない」を守って頑張っています。
クラスごとに並んで座ることができます。職員はまだ避難誘導中です。
たまごぐみはカートに乗って避難してきました。人数確認ができたので高台に避難します。津波到達まで10分を想定してみました。
あらゆる連絡方法がとれないときは避難場所を事務所入り口に張り紙をしていきます。本当に災害が起きたとき、連絡がつかないときは張り紙を見てください。慌てて書いたので文字はぐちゃぐちゃです。
緊急車両が入る場合を想定して門を開けて避難します。本当の災害の時にこの余裕はないかもしれませんが・・・
慌てず急いで避難します。避難開始から今2分です。職員の背中のリュックには非常食、オムツなど必要最低限の避難グッズが入っています。もう少し避難リュックの中も見直しが必要です。
ここで4分です。津波到達まであと6分。たまご組8人とめだか組の一人を乗せたカートはものすごく重いですが職員みんなで協力して押して引いていきます。こういう時に男性職員の力が助かります。
NTTの鉄塔の下高台まで行き着き、全員到着まで5分です。、人数確認をするまで6分でした。避難訓練をするたびに時間短縮はできています。命を守ることが最優先です。
兄弟がいるところはお兄ちゃん、お姉ちゃんが弟、妹を連れて避難します。安全を確認して帰りますが、情報が入らないときはここにいます。または山伝いに歩いて金毘羅さんに行きます。
今日は職員の数が足りなかったので、めだか組はベビーカーとおんぶで逃げました。
無事に運動場に帰ってきました。
今日は緊急連絡網の訓練はしませんでしたが、緊急時この後お子さんをどう保護者の皆さんに引き渡すか・・いろいろ検討中です。
災害時どのように避難すれば子供たちの命を守れるか・・避難訓練を繰り返しながら考え実行していこうと思います。
研修に行ったときに、「熊本地震の時は園児がいない時間の発生だったのでよかったのですが、うちの園は津波発生の連絡が来たら、車で園児を乗せて避難することにしていました。実際に地震が起きて保育園の避難経路を自動車で避難されていた人たちが身動きが取れなくなり、車を乗り捨てて走って避難されていました。ですから、園児は車での避難は不可能ということがわかり、その後は避難の仕方を変えました。」と熊本の保育園の方が言っておられました。どの避難の方法がいいかは実際に起こってみないとわかりませんが、さまざまな災害状況を想定して避難訓練をやっていこうと思います。